コンタクトレンズをつけると近くが見えないのは老眼のせい?見えない原因と対処法について医師が解説します
作成日:2024/11/13 更新日:2025/04/08
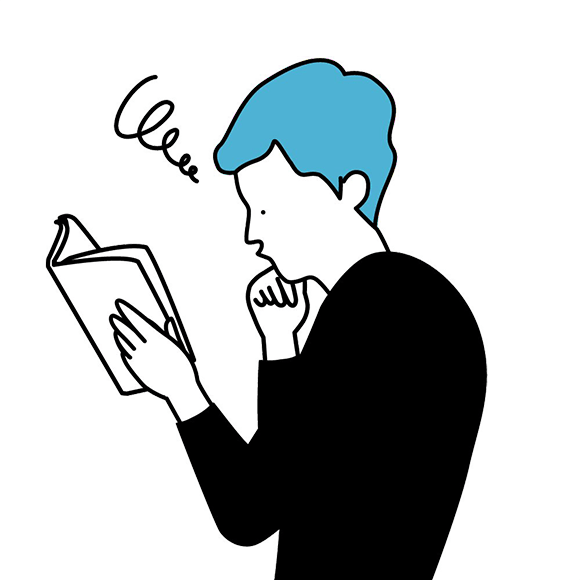
コンタクトレンズをつけると近くが見えにくい…原因は?
代表的な原因として2つ挙げられます。1つは、コンタクトレンズの度数が合っていない(合わなくなった)ということ。もう1つは、いわゆる「老眼」と呼ばれる現象が始まっているということです。この両方が原因のこともあるでしょうし、片方だけのこともあるでしょう。他の原因もあるかもしれません。原因の確定は眼科でしてもらうようにしましょう。
コンタクトレンズの度数が合っていない(合わなくなった)
今お使いのコンタクトレンズは眼科で処方してもらったものでしょうか?眼科で処方してもらったとしても、最後に検査を受けたのはいつでしょうか?
目の度数は時間とともに変化することがあります。何年も同じものを使い続けていると、気づかない間に目の度数とコンタクトレンズの度数が合わなくなることがあります。「コンタクトレンズをつけると近くが見えにくくなる」状況としては、例えば、ご自身の目の近視の度数が、最後に検査を受けたときより弱くなっている場合です。ご自身の近視が弱くなっているのにレンズの度数がそのままだと、コンタクトレンズ装用時には軽い遠視の状態となり、遠くの見え方はご年齢によってはあまり影響を受けなくても、近くは見えにくくなってしまいます。
また、まれにではありますが目の病気で一時的に近視の度数が弱くなることもあり、目の病気が潜んでいる可能性も否定できません。
そういえば、しばらく眼科で検査を受けてないなあ・・・と思われた方は眼科を受診するようにしましょう。
いわゆる「老眼」が始まっている
老眼が始まっている・・・そんなことはあまり考えたくないなあと思う方もいらっしゃるかもしれません。実は、老眼の正体である「ピントを合わせる力の減少」そのものは、ずっと前から少しずつ始まっていることで、いま始まったことでもないのです。
近視(近くは見えるが遠くは見えない)の方が多いと思いますので、近視を例にご説明します。近視の方は裸眼のときは目のピントが近くにあります。そして、遠くは見えません。コンタクトレンズを装用すると裸眼では見えなかった遠くが見えるようになるのは、レンズが目の前にあったピントをうんと遠くへ持って行くからです。その状態で近くを見るためには、レンズが遠くへ運んだピントを、自分の力で近くへ持ってこないといけません。この、「ピントを持ってくる力」は長い年月をかけて少しずつ減退してきます1)。

やや専門的な用語となりますが、この「ピント合わせができる範囲」を「明視域(めいしいき)」と呼びます。10歳代、20歳代でも少しずつ明視域は短くなるのですが、目の前10cmにピントが合わせられなくなったからといって日常生活ではなかなか気がつきませんよね。
一般の方では、目の前30cmにあるものにピントが合わなくなると、「あれ?近くが見えにくい?」と気づくようになります。そのタイミングをもって「老眼」といわれてしまうわけですが、「明視域の短縮」自体はずっと前から少しずつ、どなたの目においても起きていることなのです。
目の度数と「老眼」の関係
近視の人は老眼にならない。そんな話を聞いたことはありませんか?近視の方は裸眼でいれば近くが見えることから、このようにいわれることがあるようですが、残念ながら近視の方も老眼になります。上でご説明したように、近視の方は目のピントがもともと近くにありますので、裸眼でいる時には、近くを見るときにピントを持ってくる必要がないのです。老眼は「ピントを持ってくる力の低下」ですが、ピントを持ってくる必要がない状態ではそれを感じようがありません。「コンタクトレンズをつけてピントを遠くに持って行ったときに近くが見にくい」、という現象は近視の方にも等しくやってきます。
では、遠視の方はどうでしょうか?矯正をしていない遠視の方の場合は、「ピントを持ってくる力の低下」は、早めに気づきます。この場合、ご年齢によっては、遠視を矯正するだけでも近くが見えやすくなります。
対処法
コンタクトレンズの度数が合っていない、あるいは、合わなくなっている場合は、度数を適正化することが対処法になります。万が一にも目の病気の場合には、その病気の治療が対処法になることもあります。まずは眼科で原因を確定してもらいましょう。ここでは、いわゆる「老眼」であった場合の対処法についてご紹介していきます。
眼鏡との併用
コンタクトレンズをつけたままで眼鏡を併用して、コンタクトレンズだけでは見えにくい距離のものを、眼鏡をかけることで見えるようにする方法です。コンタクトレンズで遠くが見えるように矯正した上で、近くを見る時に眼鏡(いわゆる老眼鏡)をかけてもいいですし、コンタクトレンズで近くが見えるように矯正した上で、遠くを見る時に眼鏡を併用する方法もあります。
モノビジョン
先にお話した「明視域」を右目と左目でずらすように度数を設定する方法です。遠くの見え方は片方の目が支え、近くの見え方はもう片方の目が支える、という状態をつくり、両目を開けた状態で遠くから近くまで見えるようにします。一般的には、優位眼(利き目)は遠くが見えるようにし、非優位眼(もう片方の目)は近くが見えるようにすることが多いようですが、絶対的なルールではありません。
マルチフォーカルコンタクトレンズ
近視や遠視を矯正するレンズには度数が1つしか入っていませんが、コンタクトレンズの中には、1枚のレンズにたくさんの度数が入っているものがあります。そのようなレンズをマルチフォーカルコンタクトレンズ、といいます。 「遠近両用コンタクトレンズ」と呼ばれるものがこれに相当します。レンズに「遠くを見るための度数」だけではなく、「近くを見るための度数」や、「その間を見るための度数」が入っているため、遠くから近くまで見えるようになります。あんなに小さなコンタクトレンズに、たくさんの度数が詰め込まれているという大変複雑なつくりのものなので、メーカーや製品が違うと度数の詰め込み方も異なり、それに伴い、見え方も変わることがあります。眼科医と相談しながら、ご自身に合った見え方を提供してくれる製品を探してみてもいいでしょう。マルチフォーカルコンタクトレンズにも、ソフトコンタクトレンズとハードコンタクトレンズがあります。
まとめ
年齢とともに、あるいは目の病気に伴って、目の度数が変わることもありますし、「明視域」も少しずつ変化します。何だか見え方が変わったな、とか、疲れやすくなったな、という変化を感じたら、眼科で検査を受けるようにしましょう。
<参考資料>
1) 梶田 雅義:Ⅳ.老視における選択 2. 眼鏡処方の適応とその手順, 前田 直之 他 編:「月刊眼科診療プラクティス 95. 屈折矯正法の正しい選択」 第1版 文光堂, 2003
監修

ひぐち眼科 院長
樋口 裕彦 先生
1985年北里大学医学部眼科学教室入局。
米国Environmental Health Center-Dallas留学、北里大学医学部眼科学教室非常勤講師などを経て、1999年武蔵野市吉祥寺にひぐち眼科を開業。
2004年移転し、現在に至る。医学博士。
コンタクトレンズを探す




